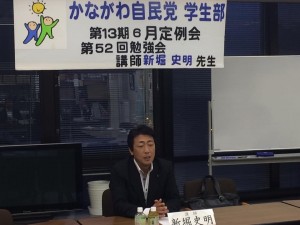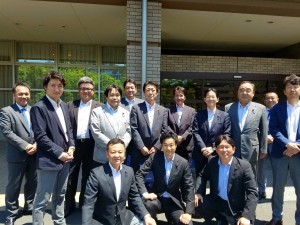8月
07
8月7日
7月の活動報告①「視察」
7月6日に第2回定例会が閉会して、あっという間に1カ月が経過いました。総務政策常任委員会の委員として初めて臨んだ議会でしたが、なんとか無事に乗り切ることができました。
常任委員会では、「働き方改革の取組について」「未病概念の普及について」「最近の地方財政をめぐる議論について」など、過去2年の産業労働常任委員会や防災警察常任委員会とは、ガラリと雰囲気が変わった質疑となりました。黒岩知事が進める「未病の改善」や昨今注目されている「働き方改革」、更には地方財政の根幹の一つである「地方交付税」のあり方についてなど、現状の県政における重要な課題についての質疑は、今まで以上に下準備をしっかりとして臨まなくてはならず、緊張の連続でした。これから1年間、しっかりと勉強をして、より積極的な議論を行い、県民生活の向上に貢献して行きたいと思います。
閉会後の7月中旬以降は、視察と選挙の毎日となりました。視察は2回。一つ目は7月7日「かながわ自民党水産業振興する議員の会」として、三崎漁港や三崎魚市場、三崎フィッシャリーナ・ウォーク「うらり」、間口漁港で「松輪サバ」の水揚げ、宮川フィッシャリーナ、神奈川県水産技術センターなどを視察しました。三崎港では、建設中の低温卸売場(冷凍マグロ用)や、新たな観光の核を目指す上でのポイントとなる二町谷の事業用地について説明を受けましたが、一番ショックだったのは、「三崎のマグロ」は日本一ではなかったということです。今やNO.1は三崎港ではなく、諸条件で優位に立つ静岡県の焼津港なのだそうです。船舶運用法の問題点や中国漁船の乱獲など、多くの課題を解決し、「三崎のマグロ」復活!を目指していくお手伝いが出来れば、と感じました。
また、間口漁港のでは、漁港の皆さんが知恵を絞って「松輪サバ」のブランド化を成功させた経緯などを伺い、感心・感動の連続でした。正直に申し上げれば、こんな小さな漁港で水揚げされるサバが、高額で取引され、今や銀座などの一流料理店でしか味わえない、と言うことが信じられませんでした。しかしそこには、漁師や漁港の皆さんの釣り方や保存方法の工夫があり、それがあの大きくて脂の乗った「松輪サバ」を安定的に市場に提供できる理由なのだとわかりました。地方創生ってこんな発想が大事なんだと思います。唯一の心残りは、「松輪サバ」が食べられなかったとこです(涙)…。お盆明けのこれからのシーズンが一番美味しいようですよ!




二つ目の視察は、7月19日に総務政策常任委員会の県内視察で、川崎市の殿町にある「ライフイノベーションセンター」「ジョンソン&ジョンソン東京サイエンスセンタ―」等へ。?そこからさらに高津合同庁舎、KSP(かながわサイエンスパーク)に伺いました。ヘルスケア・ニューフロンティアの推進を図る神奈川県の象徴的な施設と言える「ライフイノベーションセンター」では、再生医療の研究など「最先端医療の追求」と「未病の改善」と言った二つのアプローチを融合させ、そこに関わる研究者や企業に施設を提供しています。大企業からベンチャーまで、今後、市場規模の拡大が予想される再生・細胞医療産業化に向けた取組は、全国に先駆けて神奈川から発信していきます。「ジョンソン&ジョンソン」では、手術用のシミュレーターの操作を体験させていただき、ドキドキでした。
高津合同庁舎は、現在、再整備事業に向けた準備が始まっています。老朽化が進み耐震性に問題がある高津合同庁舎を民間資金を活用して再整備するという、本県初の取組です。高津合同庁舎の場所は比較的立地条件が良いことから、現在複数の企業からプロポーザル参加があり期待されています。再整備が始まれば、庁舎内にある県税事務所はKSPに仮移転することが決まっています。県有地を30年の定借で民間に再整備してもらうこの方式が成功すれば、今後の県有施設の老朽化や県財政においても、有効な選択肢が増えるわけで、是非推進して行きたい事業だと考えています。今後の進捗に注目です。




委員会と視察の報告だけでかなり長くなってしまいましたので、7月末に行われた横浜市長選挙と緑区の市会議員補欠選挙のご報告は近日中に!
8月
02
8月2日
募金活動のお知らせ
8月5日(土)11:30~12:30、上大岡駅頭におきまして、「九州北部豪雨災害募金活動」を実施いたします。お時間のある方は、是非ご協力お願いいたします。
7月
02
7月2日
6月の活動報告
中旬から、議会が本格的に動き出した6月。前半は地域のイベントや同僚議員の結婚披露宴、あるいはタウンニュースの原稿作成に時間を割くなど、久しぶりに余裕をもって過ごすことができました。
中でも、先輩の敷田議員の紹介で参加させて頂いた「ドローン研修」は、視察でありながらも、楽しい時間が過ごせました。TBSの緑山スタジオで、近年話題のドローンについて、使用における許可申請の問題点などを学び、その実用性と将来性について意見交換をしたのですが、その後実際にドローンを操縦する時間になったとたん、男ってのは、いくつになっても一人の「こども」に戻りますね!きっと自分も同じだったのでしょうが、先輩・同僚議員たちの少年のような表情が印象的でした。


その後は定例会が本格的にスタートし、日々議会に出席する傍ら、自民党神奈川県連学生部の会合で講師役を務めたり、後援会の拡大役員会を開催したり、地元の陳情を伺って区役所や警察署と打ち合わせたりと、充実した毎日を過ごすことができました。

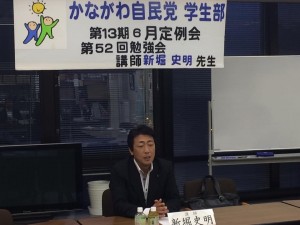
しかし、余裕を感じていたのは、ほんの2週間ほど。後半に入ると、横須賀市長選挙が待っていました。今回、見事に横須賀市長に初当選された上地克明氏は、私の「兄貴分」渋谷たけし市議の盟友であり、また私の古巣、京急電鉄の原田社長の高校時代の同級生でもあると言う、縁浅からぬ方でありました。自分としても、なんとか当選して欲しい気持ちが強く、選挙戦後半の4日間は、毎朝横須賀市内の駅頭でビラ配りのお手伝いをさせて頂きました。選挙自体が大激戦だったせいもあるのでしょうが、自分の選挙以来の大声で訴えた4日間でした。最終日には夜8時まで、横須賀中央駅で上地氏の最後の街頭演説に参加し、党や会社時代の仲間たちと久しぶりの「選挙High!」。お大いに盛り上がりました。結果は、もちろん大勝利!「ヨコスカはこんなもんじゃない!」今後の横須賀にご注目ください。



6月
15
6月15日
県政報告vol.6 掲載のお知らせ
本日配布のタウンニュース(南区版)6/15号に「県政報告⑥」が掲載されました。今回は「弘明寺特集」なので、弘明寺に縁が深い人物の一人として、編集部からお声がけ頂きました。今回は子供の頃の思い出なども載せました。南区以外の方は、是非こちらでご一読下されば幸いです。

6月
10
6月10日
5月の活動報告
毎年5月3日(ちなみに私の誕生日です!)に開催される「南区春季少年野球大会」の開会式で、地元議員団の代表としてご挨拶させて頂いたのを皮切りに、5月の活動は始まりました。5/15からスタートした平成29年神奈川県議会第2回定例会は、新しい県議会議長や各委員会の委員長を決めるための決議を行った後、6月になってから本格的な審議に入ります。佐藤光新議長(茅ヶ崎市)のもと、新たな気持ちで新年度を迎えることができました。
5月の「人事議会」が一段落すると、私を含む各議員は地域活動・後援会活動あるいは視察に時間を割くことが可能です。地元「県立こども医療センターで「馬と触れ合う会」を見学したり、若手後援会主催のBBQに参加したりと、毎年企画が盛りだくさんな5月です。
視察は、近場を数ヶ所見てきました。神奈川県農業協同組合さんのご案内で、JA厚木のファーマーズマーケット「夢未市」や、厚木の市街地でメロンをハウス栽培する農家の取組み等を視察し、都市農業の将来について意見交換ができました。
藤沢市では社会福祉法人聖隷福祉事業団の「聖隷藤沢ウェルフェアタウン」を視察。医療・福祉分野では全国有数の聖隷福祉事業団の発祥から現在の取組みを説明して頂きました。今後、医療・保健・福祉・介護サービスの分野で1都8県・140施設を展開する事業団さんと行政の連携により、県民に対するより良い医療・福祉の提供が可能になると感じました。
また同じ藤沢市で、救助犬訓練士協会(RDTA)の方々にお会いし、実際の訓練を見学させていただきました。近年、大規模災害が多発する我が国において、被災後72時間と言われるデッドラインを死守するために救助犬の活躍は欠かせません。しかし残念ながら、本県と訓練士協会との正式な出動体制や支援体制は構築されておらず、救助犬の出動は団体の自発的な行動が中心なのです。神奈川県内でいつ大規模災害が発生しても不思議ではない現在、スピード感を持った対応を推進して行くべきだと思います。
視察ではないのですが、2月の一般質問で取り上げた「子ども用車いす・バギーマークへの理解」がキッカケで知り合った、全国医療的ケア児者支援協議会親の部会・小林部会長からお声掛け頂き、「医療的ケア児者・重症心身障害児者のための災害対策会議」に参加させて頂きました。昨年度、防災警察常任委員会の委員として防災や災害対策・避難計画などしっかりと議論してきたつもりでしたが、正直こうした方々への対応・配慮などが議論されることはありませんでした。反省と共に、今後災害対策の課題のひとつとして対応して行きます。
 メロンってこうやって生るんですよ。知ってました?
メロンってこうやって生るんですよ。知ってました?
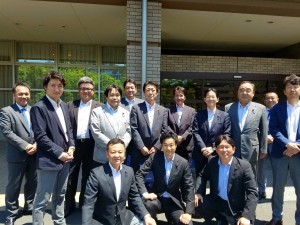 聖隷藤沢ウェルフェアタウンにて
聖隷藤沢ウェルフェアタウンにて
 村瀬ドッグトレーニングセンタ―では、ワンちゃんにやたらなつかれました?
村瀬ドッグトレーニングセンタ―では、ワンちゃんにやたらなつかれました?
 敷田前政調会長と災害対策会議に出席
敷田前政調会長と災害対策会議に出席
 誕生日は毎年ここから。南区少年野球大会でご挨拶
誕生日は毎年ここから。南区少年野球大会でご挨拶
 新風会のBBQ!三回目でやっと晴れました
新風会のBBQ!三回目でやっと晴れました